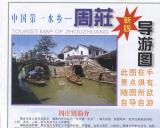2003・10・30
周庄は実は「どうしょうか?」と迷ったところだった。
ウルムチの馬さんは薦めてくれたけど人気過ぎて、まして、もし烏鎮に行くのなら行かない方がいいのでは・・・と言う意見が多かったところである。
ぼくは李黎に言った。
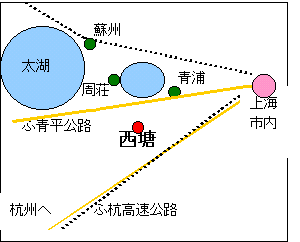
中の左あたりが入り口で、真下右に全福大橋がある。
「周庄をやめて、朱家角にしょうか?」と・・・李黎が困ったような顔で言った。
「アタシ、周庄に今度行くよ」と言ったら、友達が、「じゃあ、あそこに売っているオルゴール人形を買ってきてよ」と頼まれたらしい。
周庄へは本当は31日に行く予定であった。シータンのページで書いてあるのでここでは書かないけれど。バスの中の出来事はまるで覚えていない。たぶん、ふたりで、中国語と日本語の相互勉強をしてたのかも知れない。
周庄に着いて、とても大きいのにびっくりした。
さすが世界遺産である。
雲南の麗江とまではいかないけど観光客の受入れ体制は先の二ヶ所に較べてさすが訓練されている感じがした。
あした行くシータンとは、どんな感じだろうか?観光バスのターミナルも大きく、ツアーバスも含めかなりの台数が来ていた。
この感じでは中は混みあいそうな予感がする。バスを降りしばらく大きな通りを過ぎると長い周庄大橋を渡る。右手に八層位ある塔が見えてくる。雲海塔(②)というらしい。
さらに10分ぐらい、ぞろぞろと人の流れが続く。大きな広場にでて、巨大な門が現れる。新牌楼(①)というらしい。いわゆる、ここが周庄の入り口らしい?
そして又しばらく商店が続く、ものすごい数の輪タク③が客引き合戦をくりひろげている。
・・・・なぜか、周庄編が最後になってしまった。
記憶を蘇えらすエピソードが乏しかったというのが偽らざる事実ではあった。
そして、この周庄編が今回の「水郷古鎮紀行」のあとがきを兼ねる記録になってしまった。
周庄鎮は本当は江南地方最大の人気古鎮というよりもしかしたら中国でも一、二を争う水郷といえる。もちろん、ホームページサイトでもダントツ人気スポットである。
言い訳になるが周庄鎮にぼくの記憶が薄い理由のひとつは、ここだけ、舟に乗っての遊覧をしなかったからかも知れない。
乗る間がないほど歩くところが多く、じつは、帰りに観光マップを見てみたら行ってないところがまだ一杯あった。

見学するスポット(たいていは明・清朝時代の成功した金持ちの故家)がとても多いせいか、
さて、目的のひとつであった李黎の西洋(スエーデン)人形のオルゴール付
があったのは最初に書いた。
・・・・・・・・・「ココ。」 李黎は僕の顔を見てニッコリ笑った。
そして、なれた感じで店の中の陶器のドールを選び始めた。クラシック音楽に合わせて、人形が回るのである。
・・・・・・・・・「これ、どう思いますか?」「慶二さんドレスキデスカ?」
20こぐらい吟味して30分ほどかかって,ヤット3体のオルゴール人形がきまった。
一個200元ぐらいだったと思う。ちょっとびっくりした。ここ周庄での貨幣ベースが10元以内ぐらいで、食べ物にしても20~30元ほどだったからである。
何故、こんな高い人形を、周庄古鎮で買わなければいけないのか?分らなかった。
准海路あたりの高級おしゃれ店で見つけそうな品物と思えた。
我問李黎:李黎洋娃娃周庄的原物或者特産?
「この人形、ここのオリジナルなの?李黎。」
我想大概不一 「違うんじゃない。」・・・と答えが返ってきた。
「ここにしかない物」というよりこんなところで買うよりと・・・思ったけど、
・・・・・・・・・「よかったね!割らないように気をつけなくちゃ・・・」
満足そうな顔をしている彼女をみてて、疑問を投げかけるかわりに、口から出たコトバは反対のものだった。
もっとも、そのへんの言い回しを中国語で、とても表現できる学力もなかったけれど。
大きなマップを頼りに二人は歩いた。「一番,はずれまで行ってみよう」
南北市河に沿って富安橋を渡ると有名な沈(Shen’sResidence)庁がある。そこを出ると南市街が南湖まで続いている。この先が周庄のはずれということになる。
相かわらず人の波は途切れない。静かな古鎮という雰囲気はとてもない。太鼓橋の上も人の波、記念写真も絵にならない感じである。
歩いていると、一人の客引きが何やらしっこく李黎に言い寄っている。李黎が嫌がってる風である。足が速くなった。
「ゼンマラ? どうかしたんですか?」ぼくは訊いた。
・・・・・・「我不喜Fan算命suanming」「わたし、あのこと、スキデナイ!」
・・・・・・・「なんのこと?」
・・・・・・・「いろいろなこと、あてること・・」
意味が分らず、多分、ゲームか、何かかな、と思いながら、「あとで、辞典で見てみよう。」
と思いながら歩くうち李黎が「ここもそう。」と言ったので、見ると、長い箸が沢山立ててある。
ハッと気がついた。・・・・・「占い師だ!」と。
たぶん、こんな事で李黎を誘っていたのかもしれない。
・・・・・・・「我馬上就給ni算!?」「看ni的面相一点ル也有結婚運??」とかなんとか。
ほどなく小さな門をくぐると前方に大きな湖が広がった。南湖である。
はるかといえば大袈裟かな?と思えるぐらいな距離に、長い橋が架かっていた。
マップを見ると全福大橋と書いてあった。
そこは船着場なのか小さな漁船が5艘ほど3メートル程下に係留されていて、水の中に網があり、よく見ると蟹が何匹か入っていた。
うしろには5メートル四方の水槽があって男がひとり竿を出していた。釣堀だろうか?
僕たちは、橋の見える高台にあるベンチに腰をかけた。
李黎がペットボトルの烏龍茶を買ってきた。
・・・昨日、魯迅公園に行くときに、駅前で買ったクッキーと小面包を下げ袋から出してふたりでぱくぱくほおばった。まぁ、昼ごはんといったところだった。
そういえば、昨日も魯迅公園の大きな池の前の石のベンチに腰掛けて、同じように・・・・・・・・クッキーと小面包を食べたのを思い出した。
昨日、ベンチで何をぼくらは話したのだろう?「向こうに見える木は何の木?」それぐらいは思い出したけど。あとの会話は思い出せなかった。
そして、今日も、ぼくたちはあまり会話はしていない。(・・・・と、書いている日があの時から二ヶ月近く過ぎているので、もしかしたらぼくらは、もっといっぱい話のキャッチボールをしてたのかも知れない。)
今、思い出していて、その時、李黎の存在が負担になっていた、ということはなかった。
来年のことを考えていた。
過ぎていく一年の早さを感じながら、自分との約束をまずひとつ果たすべくチャンスの年が目の前に来ていた。
(運命は自分で切り開くもの。)よく聞いてきたこの言葉を否定し続けてきた40年の現役生活だったような気がする。
他力を主張される作家・五木寛之氏に共鳴しているぼく。
「この世は自分の思う通りにはいかないもの。」
「生まれてくるのも、来る時も、場所もすべて自分の意思ではどうにも出来ない。」
「大きな河の流れに任す小舟に乗っている」
・・・・・・・・ように人は、自分の力ではどうしょうも出来ない運命というものに身を委ねている。
・・・・・・・・・・・・・・
「人は好きなことをしたいと思う。」しかし、人生はおもうにまかせぬものである。
好きであっても素質がない場合もあり、素質があっても環境や運に恵まれず,好きでない
世界で一生を送らなければならないこともある。そういう例はいくらでもある。
こう考えてくると、ブッダが〈四苦=生老病死〉として思うに任せぬこと四つの最初に、まず(生)をおいたことの重さを、つくづく感じないではいられない。〈生)にはまた、生まれてくること、そして生きていくこと、の二つの面がある
・・・・・・・・・・・・・・・・・
生まれてくることは与えられたことだとしても、生きていくことまで運命の糸にあやつられて過ぎてゆきたくはないものだ。
「水は高いところから低いところへ流れる」もの、強い自我(自分のわがまま)は捨てて生きてきたように今までの自分は思う。それは我必為ではなく我強想の精神だったような気がする。
しかし、考えてみると我自強想こそ自分の運命を切り開くキーに他ならない。
李黎が「占いが嫌いだ。」という理由は何なのだろう?
ぼくは中国語の語彙がもっと豊富にあったらどうしても聞いてみたい。と思った。
「算命」とはよく言ったものだと思う。命を計算する。まさか、「あなたはあと何年いきられるます。」と宣告することではないだろうが、来年中国に行ったら、ひそかに算命をしてもらいたいものである。
あとがきもそろそろ終わりが近づいてきた。
長い間、ぼくの、読みづらい日記「江南水郷紀行」にお付き合い頂き感謝します。
来年のニーハオ!中国はどんな風になるのか?
多分、毎日の生活レポート(まあ、絵日記みたいなもの)になると思う。
掲示板風の形でやりとりが出来るとおもしろいかな?とも思っています。
もつとも、休みに名所古跡を訪ねた時は、ニーハオ形式で書くつもりでいます。
・・・・・・しばらく再見!!!!
私達は人間として地上に生まれたというおおきな運命を受けている。
そして、どんなにながくとも百年前後でこの世から退場するという運命をあたえられて生まれた。アジア人としての肌の色と体質をあたえられ、20世紀から21世紀への時代に生きている。それは私たちの運命である。
又私達はある家族の下に、特定の血液型因子と個性を与えられ生まれたそれは宿命である。私達はそれを否定することができない。
運命を大きな河の流れ、宿命をその流れに浮かぶ自分の船として、そこから出発するしかないのだ。 五木寛之「人生の目的」より。